退職の意思を伝えた瞬間、上司や人事から
「考え直せない?」
と、引き止められるケースは珍しくありません。
「待遇を改善する」「もう少し頑張ってほしい」などと言われると、迷いが生じるかもしれません。
しかし、この瞬間こそ冷静さが必要です。
本記事では、退職時に引き止められたときの理由・対応例・注意点を、詳しく解説します。
なぜ引き止められたのかを理解する

まずは、引き止められる背景を確認してみましょう。その理由を知ることで、適切な対処法も見えてきます。
退職の引き止めには、大きく分けて会社側の理由と上司個人の理由があります。
会社側の理由
引き止めを行う会社側の背景としてよく挙げられるのは以下のような理由です。
人員不足、後任育成の負担
突然の退職は、業務を回すための人手不足を招きます。
特に専門知識や経験を持つ社員の場合、即戦力の代わりを見つけるのは容易ではありません。
新人や異動者を育てるには時間とコストがかかるため、会社は可能な限り現状維持を望みます。
プロジェクト進行中での離脱回避
大型案件や重要プロジェクトの最中にメンバーが抜けると、進行スケジュールや品質に影響します。
クライアント対応や納期のプレッシャーが強い場合、「せめてプロジェクト完了までいてほしい」という要望が出やすくなります。
優秀な人材流出防止
全体の戦力低下はもちろんですが、高い成果を上げている社員や社内で信頼の厚い社員が辞めると、周囲への波及効果(モチベーション低下・連鎖退職)が懸念されます。
会社としては「他の人材に影響を与える前に」思いとどまらせたい心理が働きます。
上司個人の理由

会社側だけではなく、引き止めを行う背景には上司個人の理由がある場合もあります。
自分の評価や管理責任への影響
部下の退職は、管理職のマネジメント能力不足として評価される場合があります。
特に複数の部下が短期間で辞めると「職場環境に問題あり」と見なされ、上司自身の人事評価や昇進に響く可能性があります。
チーム内の士気低下防止
メンバーが抜けると、残る社員の負担が増え、士気が下がる恐れがあります。
会社側の引き止め理由とも重なりますが、「あの人が辞めるなら、自分も…」という連鎖的な離職を防ぎたいという動機もあります。
また、仲の良いチームメンバー同士だと純粋に「寂しい」という感情も混じります。
「組織的な都合」か「個人的な感情」かを整理してみる
引き止めをされた場合は、一度それが会社全体の組織的な都合なのか、上司の個人的な感情なのか整理して、一旦状況を確認してみましょう。
自分の退職理由とゴールを再確認する

引き止めにあった時、揺らいでしまう理由は様々ですが、多くの場合共通しているのは、退職理由が曖昧なままという状態です。
「なぜ辞めたいのか」「辞めた後どうしたいのか」を再整理してみましょう。
※整理の仕方の詳細を知りたい方はこちらの記事などもご覧ください。
引き止めの種類と対応例

では、実際に引き止めのパターンと、その対応例をみていきましょう。
パターン1:条件改善型(給与・待遇アップ、異動などの提案)
なにかしらの条件や待遇を改善するので、残ってほしいというケースです。
会社として人材を失いたくないため、条件改善で残留を促します。
人事部や経営層も巻き込んで具体的条件を提示してくる場合もあります。
典型的なセリフ
「給与を○万円上げるから、残ってくれないか?」
「異動して環境を変えれば、続けられるんじゃない?」
対応のポイント
提示された条件が一時的なものか継続的な改善かを見極めましょう。
過去に同じ条件改善を提示されたが、実際には変わらなかったという事例も少なくありません。
判断は感情ではなく、冷静に数字や契約条件で確認していきましょう
また、そもそも自身の退職理由が、その改善により本当に解消するものなのかを改めて考えることも重要なポイントです。
特に仕事のやりがいやスキル面でのキャリアアップを望んで退職を決めた場合は、待遇の改善が行われても、結局また同じ理由で悩むことになるケースが多いです。
回答例
「ご配慮いただきありがとうございます。ただ、私が退職を決めたのは待遇だけが理由ではないため、気持ちは変わりません。」
パターン2:感情訴え型(人間関係や情での引き止め)
上司や同僚が感情的なつながりを理由に残留を求めるパターンです。
特に長く勤めた職場や、チームワーク重視の環境で多いケースです。
典型的なセリフ
「君が抜けたらチームが困るよ」
「○○さんも寂しがるし、一緒に頑張ろうよ」
対応のポイント
関係値を築いてきたチームほど気持ちが揺らいでしまうものですが、情に流されて残っても、本質的な問題は解決されない場合が多いです。
感謝の気持ちはしっかり伝えつつ、退職の意思は変わらないことを明確にしましょう。
回答例
「皆さんと働けたこと、本当に感謝しています。ただ、自分の将来を考えて決断したことなので、この気持ちは変わりません。」
パターン3:脅し型(不利益や圧力をちらつかせる)
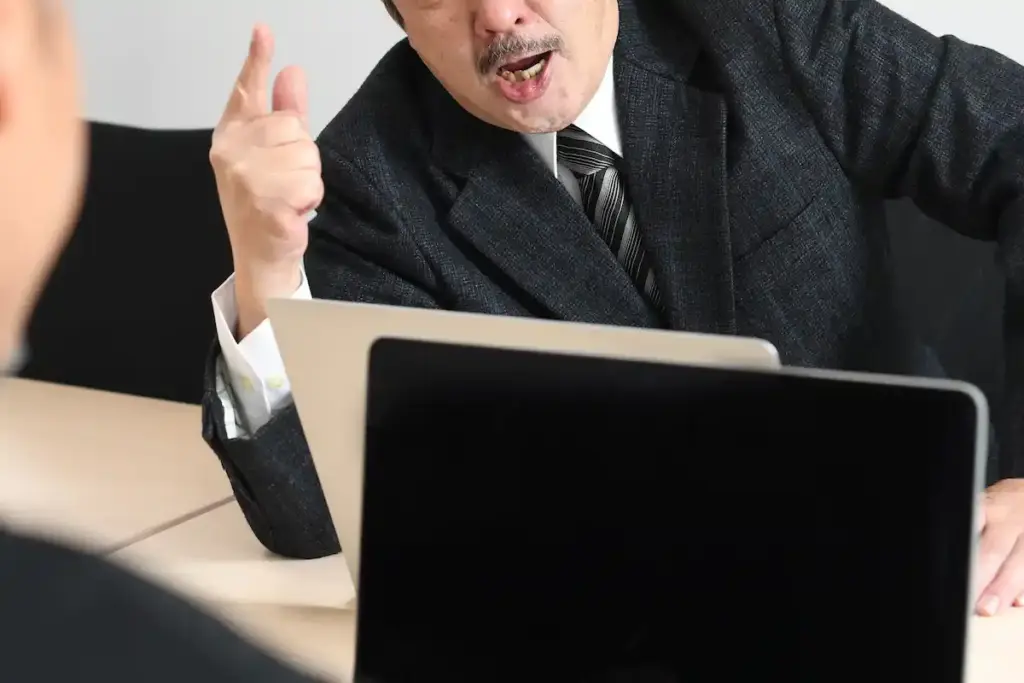
退職を思いとどまらせるため、法的根拠のない不利益をほのめかすパターンです。
時には就業規則や契約内容を都合よく解釈してくることもあります。
典型的なセリフ
「このタイミングで辞めたら、次の会社にも悪影響が出るよ」
「今辞めたら有給は消化できないかもしれない」
対応のポイント
法律や労働契約の内容を確認しましょう。
また、圧力を感じたら、記録を残すことが非常に重要です(メモやメール保存)。
必要であれば、労働基準監督署や弁護士、キャリアのプロなど第三者へ相談することも検討することをオススメします。
回答例
「契約上の権利と義務については確認済みです。ご心配いただきありがとうございますが、予定通り退職させていただきます。」
パターン4:延期要請型(退職日は認めるが時期を遅らせたい)
人員不足や業務の引き継ぎを理由に、退職日を先延ばしするパターンです。
一見合理的ですが、、ズルズル延びる危険もあります。
典型的なセリフ
「せめて後任が育つまで、あと3か月いてほしい」
「このプロジェクトが終わるまで頼む」
対応のポイント
延期する場合は必ず期限を明確にしましょう。
あわせて、延期によって自分の転職計画や生活に支障がないかも検討します。
本来は法律上「退職の意思表示から2週間(民法627条)」で退職可能ですが、円満退職を望むなら現実的な折衷案も検討することが大切です。
回答例
「引き継ぎは誠意を持って行いますが、次の予定もあるため、〇月〇日が最終出社日となります。」
円満に対応するためのコミュニケーション術

引き止めを受けても感情的にならず、相手の面子も保ちながら自分の意思を通すポイントも押さえておきましょう。
ポイント1:基本は「感謝+理由+決意」の三点セット
感情的な反発や無言拒否は関係を悪化させやすいです。
「お世話になった感謝」
↓
「退職理由の概要」
↓
「決意が固いこと」
を順に伝えると、相手が受け入れやすいため、順番を意識しましょう。まずはじめにお世話になった感謝を伝えることが大切です。
会話例
上司:「まだ考え直す余地はあるだろう?」
あなた:「これまで本当に多くのことを学ばせていただき、本当に感謝しています。ただ、自分の将来を考えて決めたことなので、この決意は変わりません。」
ポイント2:即答せず、ワンクッション置く
引き止められた場面で即答してしまうと、感情的な応酬になりやすいです。
「一度持ち帰って考える」と伝えると、自分も冷静に判断できますし、相手も頭を冷やす時間を設けることができます。
会話例
上司:「待遇を改善するから、もう少し続けないか?」
あなた:「ご提案いただきありがとうございます。大切なことなので、一度持ち帰って考えさせてください。」
ポイント3:書面やメールで退職日を再確認する

口頭での合意だけでは、後で「言った・言わない」になりやすいため注意が必要です。
話し合い後、メールで退職日と引き継ぎスケジュールを記録に残しておきましょう。
メール文例
件名:退職日および引き継ぎについて
〇〇部長
本日はお時間をいただきありがとうございました。
お話の中で、最終出社日を〇月〇日とし、それまでに引き継ぎを完了することで合意いただきました。
今後も円滑な業務移行に努めますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ポイント4:感情的な圧力への対応は冷静に
脅しや不利益提示を受けても、感情で反応しないようにしましょう。
必要に応じて「確認します」とだけ伝え、その場で結論を出さないことが重要です。
会話例
上司:「このタイミングで辞めたら、迷惑がかかるぞ」
あなた:「影響については理解しています。可能な限り引き継ぎを行いますので、〇月〇日を最終日として進めさせてください。」
ポイント5:残留を選ぶ場合も条件を明確化
条件改善を受け入れる場合は、口約束ではなく、必ず文書で記録を残しましょう。
記録には、仕事内容や待遇改善の期限・金額を明記します。
会話例
「今回提示いただいた条件で残る場合、内容を文書にまとめていただけますでしょうか。今後の業務計画を立てやすくするためです。」
引き止めを受け入れる場合の注意点

退職の意思を伝えたあとでも、提示された条件や環境の変化が本当に自分の希望に合致する場合、残留を選ぶこともあります。
ただし、この場合は次の点に注意が必要です。
注意点1: 条件は必ず文書化する
口頭での約束は後で反故にされる可能性があります。
給与額や役職変更、勤務時間などは書面やメールで明確に残しましょう。
注意点2:過去の不満が改善される保証はあるか
異動や仕事内容の変更があっても、根本的な職場文化や人間関係はすぐには変わりません。
短期的な改善だけで判断せず、長期的に働き続けられる環境かを見極める必要があります。
注意点3:将来の転職計画も視野に入れる
一度辞めたいと伝えた社員は、会社から「いずれまた辞める可能性がある人」と見られる場合があります。
残留後も自分のキャリアプランを持ち続け、転職市場の動向も把握しておくと安心です。
まとめ:自分の軸をぶらさない

退職時の引き止めは、会社や上司の都合だけでなく、善意やチームへの思いからくる場合も多くあります。
ただし、どのような背景であれ、自分のキャリアの軸をぶらさないことが最優先です。
ポイントは次の3つです。
・引き止められる理由を理解し、感情ではなく事実で判断する。
・条件や提案は冷静に検討し、必要なら記録を残す。
・「感謝+理由+決意」で誠意をもって伝えることで、関係を損なわずに次のステップへ進む。
引き止めは一時的な出来事ですが、キャリアの選択はその後の人生を大きく左右します。
その場の雰囲気や情に流されず、自分にとって最善の道を選びましょう。
※この記事を読んだ人が合わせて見ている記事
「とはいえ、やはり不安…」そう感じたら、プロの力を借りてみませんか?
「自分の状況だとどんな点に気を付ければいいのか知りたい…」 「プロに具体的にアドバイスしてもらいたい…」
というご不安をお持ちの場合は、ぜひキャリアの専門家への相談も検討してみてください。
ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援実績をもとに、ご自身での退職を支援するサービスをはじめ、様々なキャリア支援のサポートをご提供しています。
▶個別の状況に応じた退職時のポイントをチェック
▶退職を上司に伝えるための事前ロールプレイの実施
▶退職トラブル発生時のサポート
ご自身の新しいキャリアを築くために、一歩踏み出すあなたを、私たちプロが全力でサポートいたします。
→ 退職支援サービスの詳細は下記よりご確認ください
<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」
そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。
会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。
<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!
✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK
✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき
「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。
<書類通過パス>
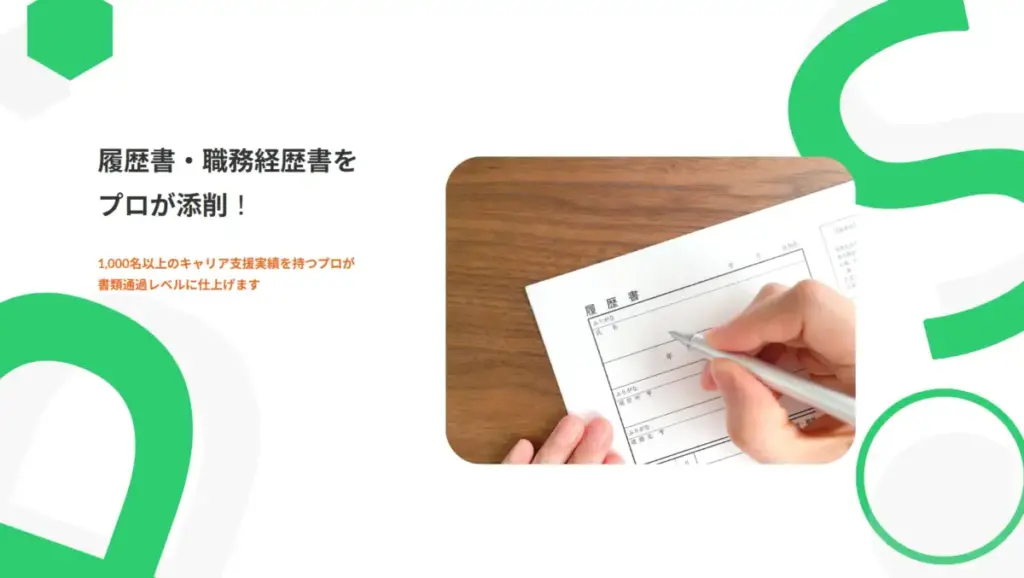
履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。
納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。
書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

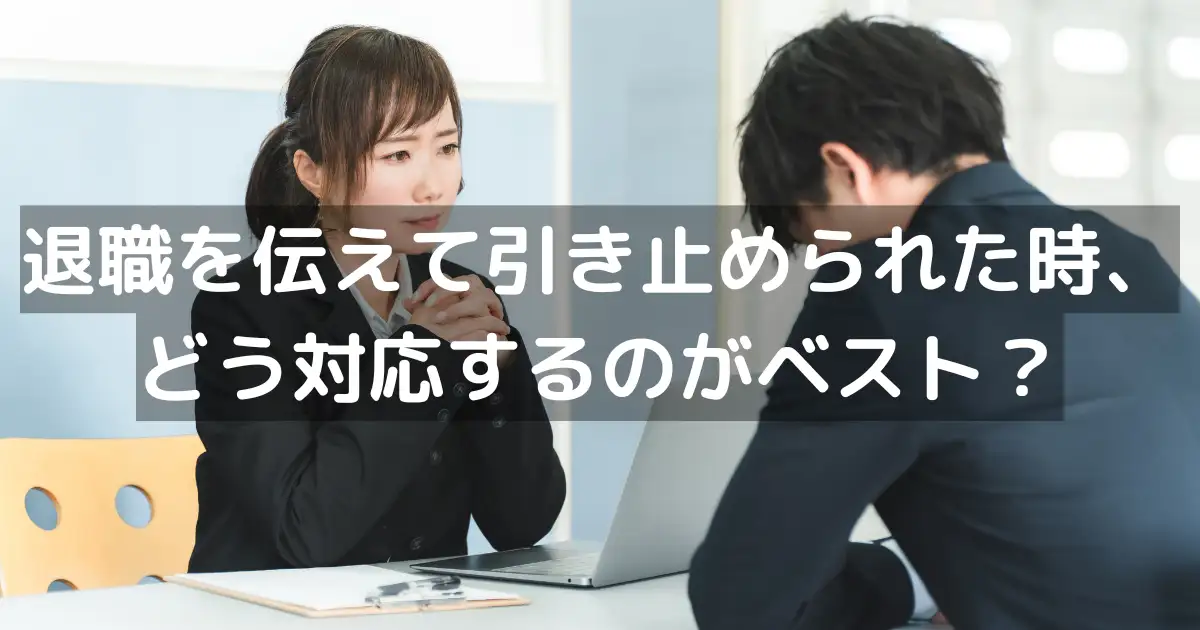

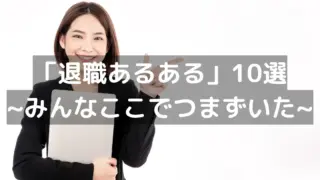
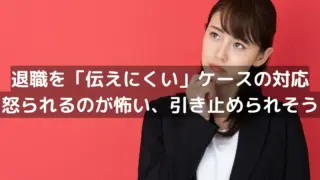
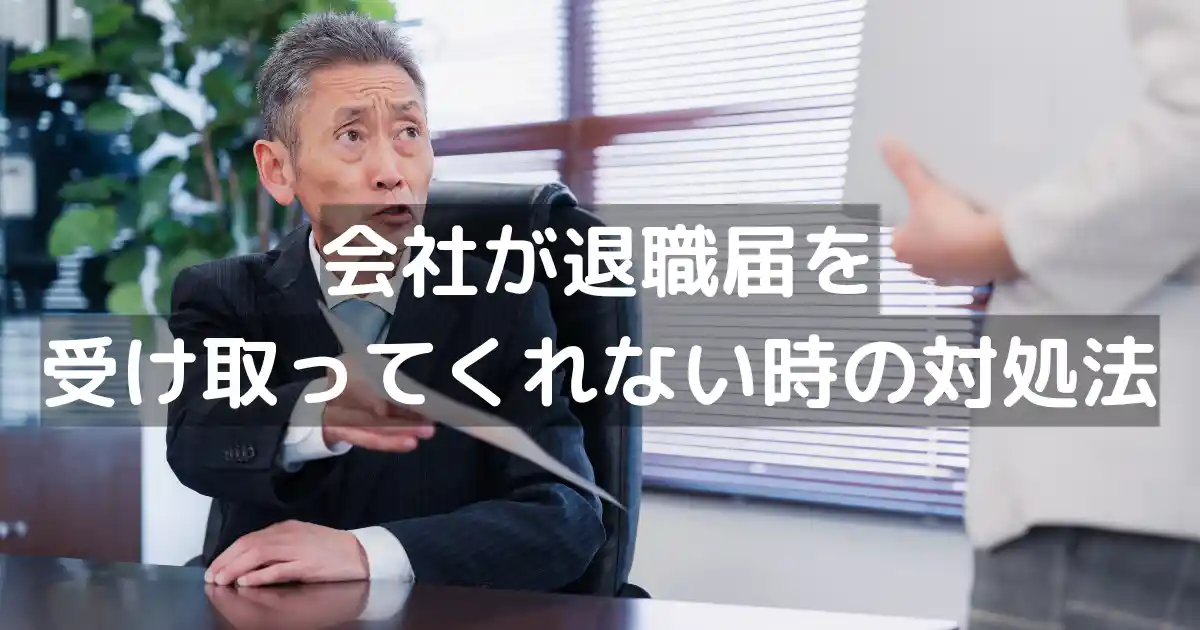
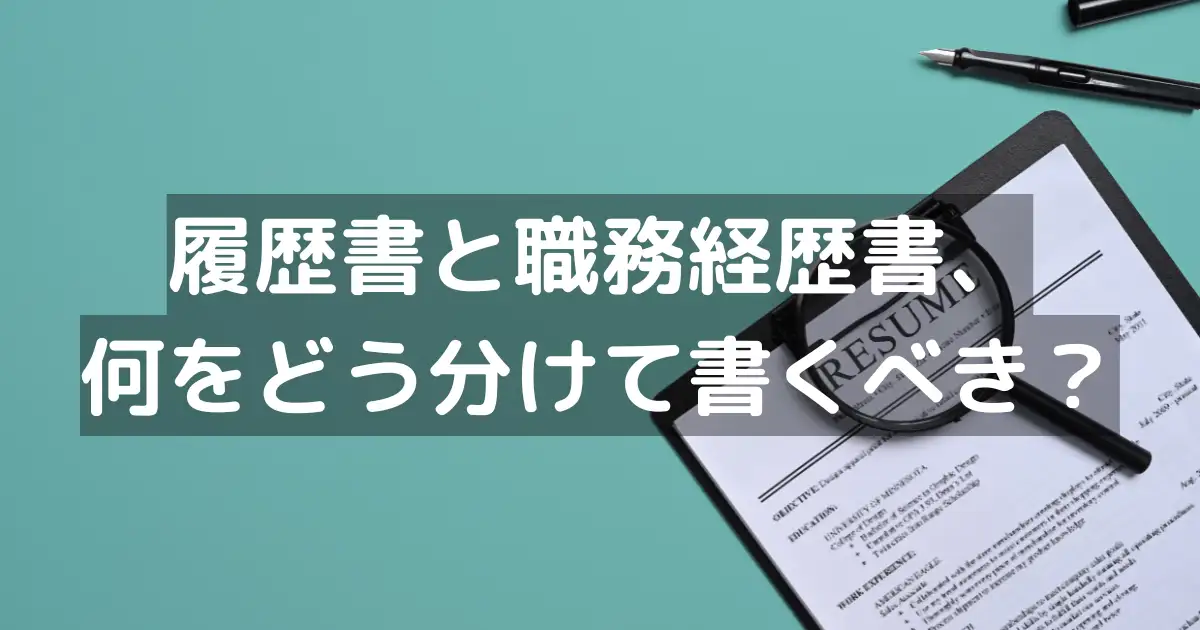
コメント