「もう辞めるんだから、関係ないでしょ」
と思われる方もいるかもしれません。
でも実は、その“辞め方”が、あなたのこれからのキャリアに影響を与えることもあるのです。
辞めるのであれば、揉めて辞めるよりは、円満に辞めるにこしたことはありません。
では、実際にどんなことに気をつければいいのでしょうか?
この記事では、引継ぎでありがちな4つの失敗ケースと、円満退職に必要な5つの引継ぎマナーを具体的に解説します。
※退職日と有休消化の調整について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
そもそも円満退職とは?
よく聞かれる円満退職という言葉ですが、そもそも円満退職とはなんでしょうか?
なにをもって「円満」とするかは、人によって異なるかもしれませんが、一般的に共通しているポイントは下記です。
・感情のもつれがなく、業務上の混乱も最小限
・退職後の人間関係を保てる
・引継ぎがきちんとしている
この中でも大きなポイントとなるのは、「引継ぎ」です。
引継ぎはなぜトラブルになりやすいのか:よくあるトラブル例

引継ぎのゴールは、
「自分のしていた仕事を自分がいなくても問題なく人に対応してもらうようにする」
ことです。
言葉にすると簡単ですが、実はこれが意外と難しいのです。
ここでは、よくあるトラブルになりやすいケースと対策を紹介します。
ケース1:スケジュールに余裕がない(退職までの時間が短い)
雇用期間のない正社員でも、民法上(民法第627条)は2週間前に退職を申し出れば会社を辞めることができます。
ただ、実際に退職まで2週間しかない状態だと、引き継ぐ側も引き継がれる側も、準備が間に合わずトラブルのもとになりやすいです。
引き継ぐ側はまだしも、引き継がれる側は、通常業務にプラスして引継ぎ対応が発生している場合も多々あります。
また、たとえ1カ月前など一般的な余裕をもって退職を申し出た場合でも、有休消化で実際の勤務日は残り少なかったり、その残り少ない勤務日の中で引き継がれる側とのスケジュールがあわなかったり、実際引き継ごうとしたら、ぜんぜん時間が足りないというケースはよくあります。
対策
具体的な期間は会社や業務の状況によりますが、スムーズな引継ぎのためには、引き継がれる側も含め、ある程度余裕をもったスケジュールを考えておきましょう。
ケース2:何をどこまでやるかの基準があいまい
「このタンクの液体が少なくなったら、十分な量まで液体を足す」
良いマニュアルと悪いマニュアルの話などで、よく出てくる例えですが、これだと人によって「液体が少ない状態」の判断があいまいになってしまいます。
対策
「タンクの赤のラインより少なくなったら、緑のラインまで液体を足す」
など、客観的に分かる具体的な基準を設定しましょう。
だれでもわかるような基準を設けることで、トラブルを防ぐことができます。
ケース3:それをする理由や背景まで伝えず表面的な引継ぎに留まってしまう
「Aの時はBをすればいいから。CだったらDをすれば大丈夫」
一見引継ぎとしては問題なさそうですが、引継ぎ内容がこれのみだと注意が必要です。
なぜなら、そうする理由や背景が伝わっていないからです。
対策
「Aの時にBをする必要があるのは、関係する〇〇がこういう仕組みになっているから」
など、その裏にある理由まで伝えましょう。
引継ぎ業務自体への理解が深まるのはもちろん、万が一イレギュラーが起きた場合でも、
「この仕組みということは、この場合はこうすればよいのかも」
と、対応ができる可能性も高まります。
ケース4:「属人化された業務」のまま辞めようとする
どれだけ丁寧に引き継ごうとしても、「そもそもその業務が他の人に引き継げる設計になっていない」場合、大きな問題が残ります。これはいわゆる業務の属人化と呼ばれる状態です。
たとえば、
・業務の進め方や判断基準が自分の頭の中にしかない
・ファイルやツールの管理方法が独自で、他の人が探せない
・顧客対応が“個人の付き合い”ベースになっている
このような状態で退職すると、引き継ぐ側は何をどうすればいいかすら分からず、組織に大きな混乱を残してしまう可能性があります。
実は、これは想像より難しい問題です。
なぜかというと、こういったケースは、「自分の中では当たり前になってしまっていて、わざわざ言うことでもないだろう」と、認識の範囲外になっているからです。
つまり、ほぼ無意識のため、自分で気づくことが困難なことが多いのです。
対策
退職する前に、後任の方や第三者に実際に引継ぎマニュアルを試してもらい、自分がいなくても問題なく対応ができるのか、穴を確認してもらうことがオススメです。
属人化された業務は、ケース2やケース3のような「伝え方」の問題以前に、業務設計そのものに課題がある状態です。引継ぎのマニュアル作成の際は、自分の業務をきちんと棚卸しして、どこが属人化しているか、洗い出しましょう。
円満退職に向けた「引継ぎマナー」の基本5選

それでは、このようなトラブルを回避するためにも重要な、引継ぎにおけるポイントを押さえておきましょう。
基本1:業務リストの棚卸を最初に行う
まずはここからです。
自分が担当している業務、関係者、進行中のタスクなどを、すべて洗い出して一覧化しましょう。
これを怠ると、この後の引継ぎ準備がスムーズに進みづらいだけではなく、後になって「あっ、あれ引き継ぎ忘れていた!」と焦ることにもなりかねません。
基本2:「どの程度まで伝えるのか」のすり合わせを上司と行う
引継ぎ範囲や優先順位を主観で決めないようにしましょう。
基本1で作成した一覧をもとに、上司に相談するのがオススメです。
基本3:書類・データは「引継がれる側」目線で整理
第三者がみても何の書類やデータなのか分かるようにしておきましょう。
また、ファイルの命名ルールや、アクセス方法もきちんと明記しておきましょう。
自分だけがわかる状態では、後任者が業務を開始するまでに無駄な時間や手間がかかってしまいます。
基本4:引継ぎマニュアル書+口頭の両方を意識する
資料だけを残すでもなく、口頭だけで済ませるのでもなく、「資料も残すし口頭でも伝える」形で引継ぎは進めていきましょう。
どちらかだけだと、トラブルにつながる見落としを発生しがちです。
基本5:ネガティブ情報もきちんと引き継ぐ
ミスや未解決の課題は、隠すことなく誠実に伝えましょう。会社への迷惑はもちろん、隠すことで不必要に問題が大きくなり、まわりまわってあなたへの不利益にもつながります。
正直に伝えることで、後任者が早期に対処でき、会社への被害を最小限に抑えられます。そして、それが結果的にあなたの信頼にもつながるのです。
退職は終わりじゃなくて、”次につながる”通過点

よい引継ぎから生まれる円満な退職は、礼儀でもあり次のキャリアへでも役立つ信頼につながります。
辞め方もあなたのキャリアの一部なのです。
本記事でご紹介したようなポイントを押さえて、
あなたの退職が単なる「終わり」ではなく、次のキャリアへの「確かな一歩」となる
ように、円満な引き継ぎを実践しましょう。
もっと実践的なサポートを受けたい方へ
ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援を行ってきたプロによる円満退職のサポートも行っています。
円満退職ができるかどうかで、次の一歩が大きく変わることもあります。
「一人ではやはり不安」「何から手をつければいいかわからない」という方は、まずはお気軽に下記サイトより無料相談をご利用ください。
<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」
そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。
会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。
<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!
✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK
✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき
「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。
<書類通過パス>
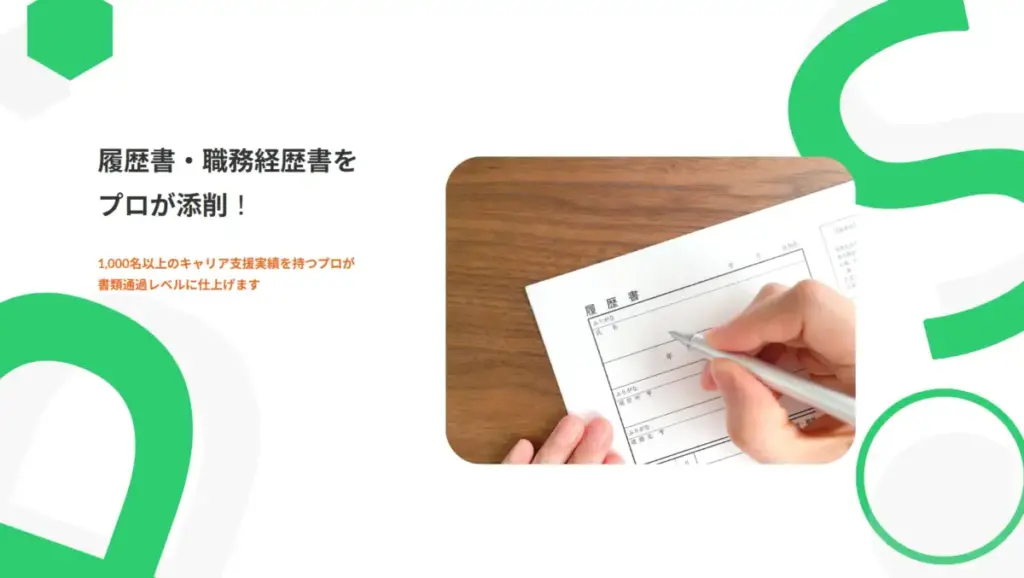
履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。
納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。
書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

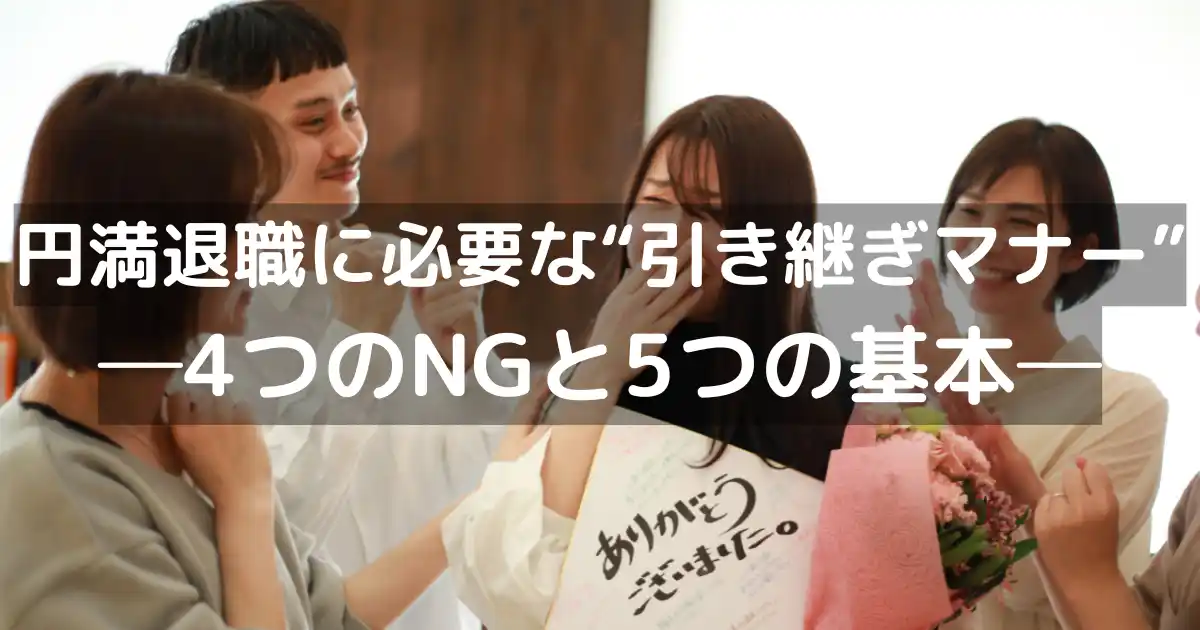
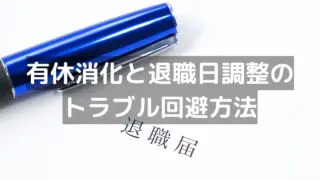

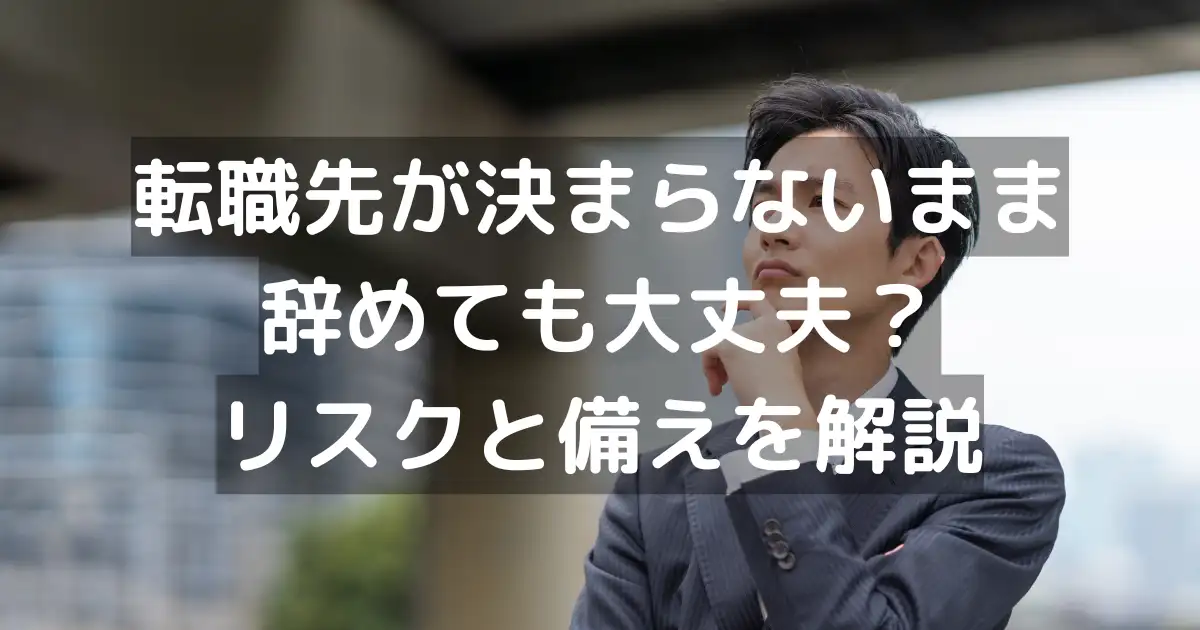
コメント