退職は人生における大きな節目のひとつです。
「もう辞めよう」と決めるまでにも葛藤がありますが、実際に退職を進めてみると、想像以上に手間や悩みが多いもの。
上司への伝え方、退職日の調整、有休消化、引き継ぎ…そして退職後の生活まで。
多くの人が似たようなポイントでつまずきます。
本記事では、退職経験者が「ここで困った」と感じやすい“退職あるある”を10項目に整理し、それぞれの対応策を解説します。
これから退職を考えている方にとって、余計なトラブルを避けるヒントになれば幸いです。
退職あるある①:退職を切り出すタイミングに悩む
最初のハードルは「いつ退職の意向を伝えるか」です。
年度末やプロジェクト終了時を狙う人も多いですが、業務の状況や上司の忙しさを気にしてしまい、なかなか言い出せないケースも多いです。
対応策:
就業規則で「退職は〇か月前に申し出ること」と規定されていることが多いため、最低でも1~2か月前には伝えるのが望ましいです。
タイミングを迷う場合は、定例の1on1や面談の機会を活用するとスムーズに切り出せます。
※具体的なベストタイミングはこちらをご覧ください。
退職あるある②:直属の上司に言い出しにくい
「裏切るようで言いづらい」「怒られるかもしれない」と悩む人は少なくありません。
特に信頼関係が深い上司ほど、切り出しにくさは強くなります。
対応策:
退職の意向は基本的には直属の上司から伝えるのがルールです。
気持ちを整理し「お世話になりましたが、今後の成長のために転職を考えています」とシンプルに伝えるとよいでしょう。
感情的にならず、事実を淡々と伝えることが大切です。
※さらに具体的な方法はこちらもご覧ください。
退職あるある③:有休消化の調整でモメる
「人手不足だから有休は取れない」と言われてしまうケースもあります。
しかし、有休取得は法律で認められた権利です。
対応策:
退職日から逆算して早めに計画を立てることが大切です。
消化できる日数を確認し、業務引き継ぎと並行してスケジュールを提示すると、上司や人事も調整しやすくなります。
もし不当に拒否される場合は、労基署に相談できることも知っておきましょう。
※よくある有休消化のトラブルケースと対応方法はこちらをご覧ください。
退職あるある④:退職日を会社都合で引き延ばされる
「せめて新人が育つまで」「プロジェクトが終わるまで」など、退職日をずるずる先送りにされるのもよくある話です。
対応策:
民法上は「退職の申し出から2週間後には退職可能」とされています。
ただし円満退職を望む場合は、現実的に1〜2か月前に伝えるのが一般的。
強く引き止められた場合も「法律上は○日をもって退職可能」と冷静に伝えることで、話が進む場合があります。
※退職を引き止められた時の具体的な対応方法に関しては、こちらもご覧ください。
退職あるある⑤:引き継ぎ資料が膨大で心が折れる
「辞める直前になって初めて、自分の業務がどれだけ属人化していたかに気づいた」という人は多いです。
対応策:
いきなり完璧なマニュアルを作る必要はありません。
大切なのは「誰が読んでも最低限分かる」こと。
業務の流れ、関係者リスト、重要なデータの保存場所などを整理しておけば十分です。
必要に応じて後任者と直接時間を取って補足説明すると、感謝されやすくなります。
※引継ぎの具体的なコツはこちらの記事もご覧ください。
退職あるある⑥:周囲に気を遣いすぎて疲れる
「自分が抜けたら同僚が困るのでは」と不安になり、過剰に残業してまで引き継ぎを頑張ってしまう人もいます。
対応策:
退職は、少なからず誰かにとって負荷がかかるイベントです。
完璧に引き継ぐことは不可能と割り切り、最も重要な部分だけを優先しましょう。
むやみに謝罪を繰り返すより、感謝を伝える方が前向きな印象になります。
退職あるある⑦:退職理由の説明が難しい
「正直に言うと角が立つ」「建前でごまかすのも不自然」と悩む人は少なくありません。
対応策:
退職理由は「スキルアップ」「キャリアの幅を広げたい」「家庭の事情」などポジティブで無難な言葉にまとめるのが安心です。
本音を全て伝える必要はなく、誠実さと前向きさを意識すれば十分です。
退職あるある⑧:最後の挨拶で何を言えばいいか困る
送別会や最終出社日の挨拶で「何を話せばいいのか分からない」と焦る人も多いです。
対応策:
長々と話す必要はありません。
「在職中にお世話になった感謝」「今後の皆さんの活躍を祈っている」という2点をシンプルに伝えるだけで十分です。
無理にユーモアを入れる必要もありません。短く前向きな言葉で締めましょう。
退職あるある⑨:社保や年金、手続きが意外と面倒
退職後に必要な手続きは想像以上に多く、忘れると生活に支障が出ることもあります。
対応策:
・健康保険
退職後14日以内に国保へ加入、または任意継続を申請
・年金
退職後14日以内に国民年金へ切り替え
・雇用保険
離職票を受け取り、ハローワークで手続き
これらは退職直後の生活に直結するので、早めに確認しておきましょう。
退職あるある⑩:退職後の「燃え尽き感」や不安
退職を終えて「やっと自由だ!」と思ったのも束の間、次のキャリアや生活費の不安に直面する人も少なくありません。
対応策:
退職後の空白期間を想定し、転職活動や資格学習、生活費の計画を事前に立てておきましょう。
もし不安が強い場合は、退職前から転職エージェントやキャリア相談サービスを活用するのも有効です。
まとめ
退職は想像以上に多くのハードルがあるイベントですが、「よくあるつまずきポイント」を知っていれば、冷静に対応できます。
大切なのは「自分のキャリアをどう歩むか」を中心に考えること。
会社や周囲に配慮しつつも、最後は自分の意思で決断するのが何より重要です。
退職はゴールではなく、新しいスタート地点。
少しの準備と工夫で、次のキャリアをより前向きに迎えることができます。
「とはいえ、やはり不安…」そう感じたら、プロの力を借りてみませんか?
「自分の状況だとどんな点に気を付ければいいのか知りたい…」 「プロに具体的にアドバイスしてもらいたい…」
というご不安をお持ちの場合は、ぜひキャリアの専門家への相談も検討してみてください。
ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援実績をもとに、ご自身での退職を支援するサービスをはじめ、様々なキャリア支援のサポートをご提供しています。
▶個別の状況に応じた退職時のポイントをチェック
▶退職を上司に伝えるための事前ロールプレイの実施
▶退職トラブル発生時のサポート
ご自身の新しいキャリアを築くために、一歩踏み出すあなたを、私たちプロが全力でサポートいたします。
→ 退職支援サービスの詳細は下記よりご確認ください
※ご相談は無料です。
<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」
そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。
会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。
<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!
✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK
✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき
「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。
<書類通過パス>
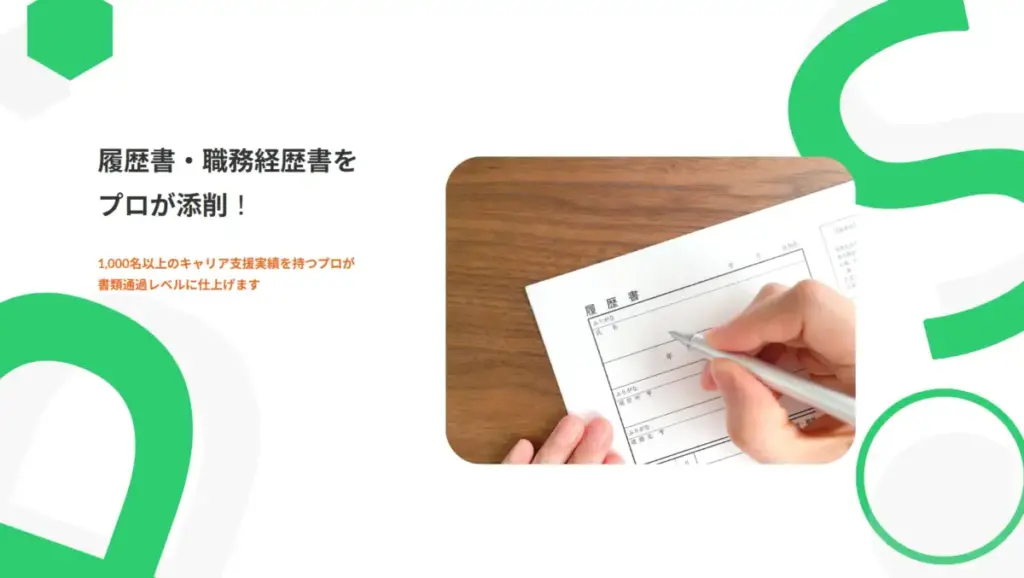
履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。
納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。
書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。

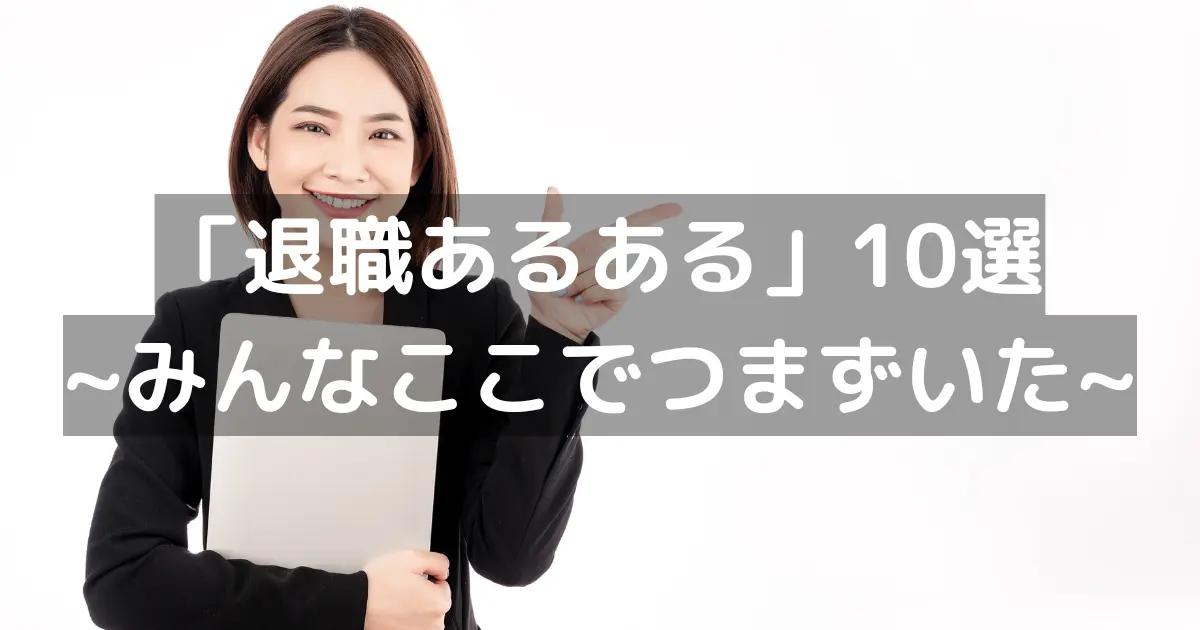

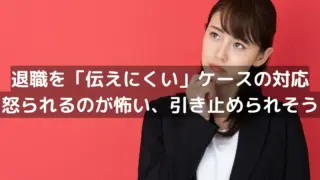

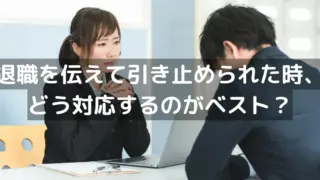

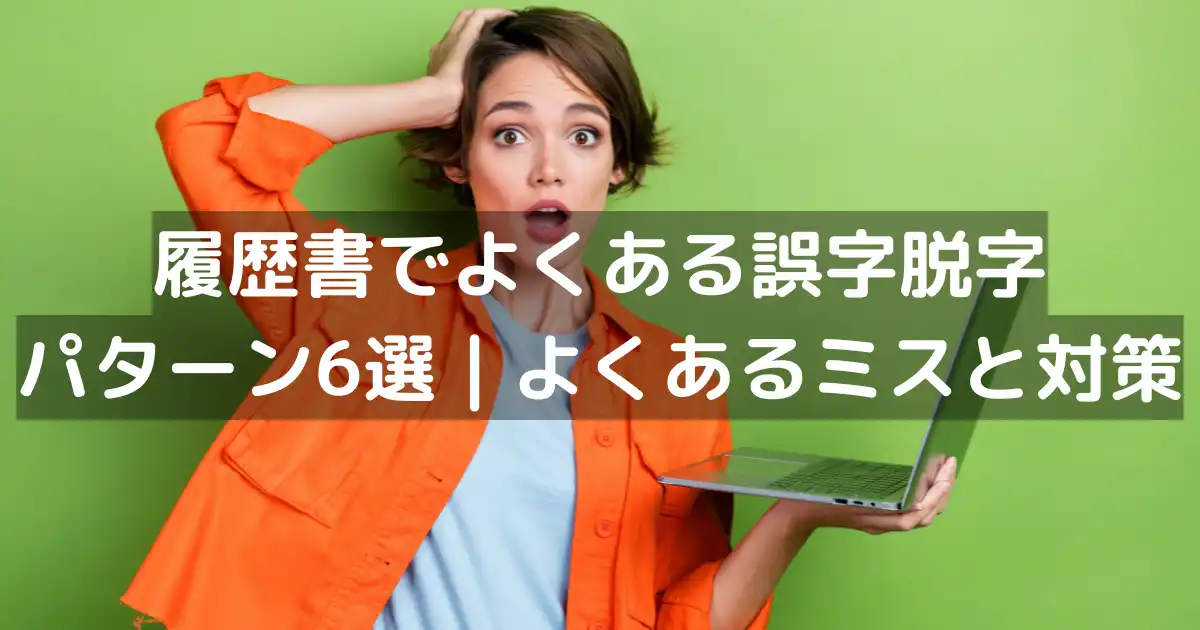

コメント