「また内定辞退か……」「来月までにあと3人決めないと」。
採用担当者のデスクには、常に時間とプレッシャーが並んでいます。
求人原稿を出し、スカウトを送り、面接日程を調整し、内定者フォローまで…
採用は終わりのないマラソンのような仕事です。
会社の成長に直結する「採用成功」は、経営陣からも現場からも注目される重要なミッション。
その一方で、「採用疲れ」や「採用バーンアウト」という言葉が現実味を帯びて聞こえるほど、担当者の心身には知られざる負担が積み重なっています。
採用担当者もまた、人を支える“人”なのです。
本記事では、採用担当者が抱える見えない負担と、疲弊を防ぐためのマネジメント術について考えます。
採用担当者が疲弊する3つの要因

要因① 成果プレッシャーの過剰化
採用は「何人採れたか」という数値で評価されやすい仕事です。
もちろん人数は重要ですが、「埋めること」が目的化すると、プロセスや質を見直す余裕がなくなります。
その結果、担当者は「常に追われている」状態になり、モチベーションが徐々に削られていきます。
要因② 社内での孤立
採用担当者は、現場からの「早く人を入れてほしい」という声と、経営からの「採用コストを抑えて良い人を入れて」という指示の板挟みになりがちです。
誰かの期待に応えようとするほど、別の誰かの不満を招いてしまう。
この「両立困難な期待」を同時に背負う状況は、担当者の心に大きな負荷をかけます。
「誰も自分の苦労を分かってくれない」と感じる瞬間が、孤独を深めます。
また、配属先の現場が採用したメンバーの育成に関心を示さない場合、「入社後の活躍」という最も重要な成果に責任を持てず、無力感を覚えることも疲弊の一因です。
要因③ “終わらない採用活動”
慢性的な人手不足が続く中、多くの企業では「採用を止めるタイミング」がありません。
常に新しい募集をかけ、常に選考を進め続ける。
目の前の仕事に追われ、振り返りや改善をする時間も取れず、疲弊が蓄積していくのです。
この「タスクの波」に身を任せるだけの状態は、仕事のコントロール感を失わせます。
採用プロセスのどこに問題があるか、どの施策が効果的だったかを冷静に分析する時間がないまま、惰性で業務を続ける状態は、担当者の仕事の意義を見失わせてしまう危険性があります。
採用疲れがもたらす組織への影響

採用担当者が疲れていると、応募者対応の丁寧さやスピードに影響が出ます。
メールの文面が少しそっけなくなる、面接中の笑顔が減る…
そんな小さな変化が応募者に伝わり、結果的に企業の印象を下げることにもつながります。
また、チーム内の雰囲気も重くなりやすく、「採用って大変だよね」という諦めの空気が広がると、優秀な担当者ほど離れてしまうリスクも。
採用を支える人が疲弊することで、企業全体の採用力が低下していく。
これは決して珍しい話ではありません。
採用疲れを防ぐマネジメント術

ここからは、採用担当者の燃え尽きを防ぐためにできる、実践的なマネジメントの工夫をいくつか紹介します。
1. 採用目標を“人ベース”から“価値ベース”に切り替える
状況によっては少し理想論的な部分もありますが、「10人採る」ではなく、「私たちの組織にどんな仲間を迎えたいか」という視点をチームで共有する。
目的が“数”から“価値”に変わることで、担当者の仕事にも意味づけが生まれます。
「誰を採るか」よりも、「どんな人と働きたいか」を話す時間を設けることが、採用疲れをやわらげる第一歩です。
可能であれば、採用担当者と現場マネージャー間で「求める人物像チェックリスト」を定期的に見直しましょう。
チェックリストにはスキルだけでなく、「行動特性」「組織文化とのフィット感」といった曖昧になりがちな要素も言語化し、擦り合わせる時間を持つことで、担当者が自信を持って選考に臨めるようになります。
※企業文化に合う人材採用に関しては以下記事もあわせてご覧ください。
2. 採用チームを“孤独にしない”
採用を人事部だけの業務にせず、経営層や現場リーダーを巻き込むことが重要です。
例えば、各部門のメンバーを面接官にトレーニングして一緒に参加してもらう、募集要件を一緒に考える。そんな取り組みが“共に採る”意識を育てます。
「採用は会社全体のプロジェクト」という文化が根づけば、担当者の孤立は減っていきます。
現場巻き込みの際、面接官へのトレーニングは必須です。
単に日程調整を依頼するだけでなく、面接での「傾聴の姿勢」や「質問の意図」までを共有することで、担当者の負担を減らしつつ、現場が採用を自分ごととして捉える機会になります。
また、現場の協力は「評価」で報いることも重要です。
3. 情報共有と振り返りの場を設ける

採用活動が一区切りついたら、“打ち上げ”や“ふりかえり会”を設けましょう。
うまくいった点、改善できる点を共有し、チームで称え合う。
この小さな「区切り」が、次の採用へのエネルギーを生み出します。
振り返りでは、「良かった点」を単に褒めるだけでなく、「なぜうまくいったのか」を言語化できると尚良しです。
成功の再現性を高めるだけでなく、担当者が自らの仕事に戦略性や専門性を見出し、「ただの作業者ではない」という自己肯定感につながります。
終わりのない業務に“終わり”をつくることは、実はとても大切です。
4. 外部リソースやツールの活用をためらわない
RPO(採用代行)やスカウト自動化ツール、求人原稿作成のAIサポートなど、今は採用を助ける手段が増えています。
「全部自分たちでやらないと」という思い込みを手放し、外部と協働することもマネジメントの一つ。
“業務を減らす勇気”が、チームを守ることにつながります。
5. メンタルケアとリカバリーの習慣化
採用担当者にも、定期的にリセットの機会を。
他部署へのジョブローテーションや、社外研修への参加、休暇の取得など、“採用”から一度離れる時間を意識的に設けることが効果的です。
「また戻りたい」と思える仕事にするには、心の余白が必要です。
採用担当者を「支える文化」を育てる

採用は、企業の未来をつくる入口の仕事です。
その責任は重いですが、本来は「人を迎える喜び」に満ちた仕事でもあります。
だからこそ、担当者が燃え尽きないように支える文化が、組織全体に必要です。
「採用を頑張る人を、会社全体で応援する」
その姿勢こそ、応募者にも伝わります。
採用担当者が誇りと笑顔を持って働ける企業は、必ず魅力的に映るものです。
まとめ:採用を「人を迎える喜び」に取り戻す

採用疲れは、担当者個人の問題ではなく、組織全体の仕組みや文化が生む現象です。
だからこそ、解決もチーム全体で取り組む必要があります。
こうした取り組みを続けていくと、「採用」は単なる業務ではなく、会社の文化を形づくる活動へと変わっていきます。
私もこれまで数多くの企業の採用サポートをさせていただきましたが、採用担当の方が笑顔でいられる会社は、やはりいい人が集まりやすいなという印象です。
採用を“こなす業務”ではなく、“人との出会いを楽しむ活動”へと取り戻す。
そんな意識の転換が、結果として採用力を高め、企業の魅力を育てていくのだと思います。
担当者の笑顔は、最も強力な採用ブランドになるはずです。
キャリアや転職のお悩みなら
ストローラー株式会社では、1,000名以上のキャリア支援実績をもとに、現職での悩みから転職活動まで幅広くサポートしています。
たとえばこんなお悩みはありませんか?
– 今の会社に不満はあるけど、辞めるべきか迷っている
– 転職したいけど、何から始めればいいのかわからない
– 自分の強みや適職がわからない
詳しくは下記ページよりご確認ください
※ご相談は無料です。
<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!
✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK
✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき
「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。
<書類通過パス>
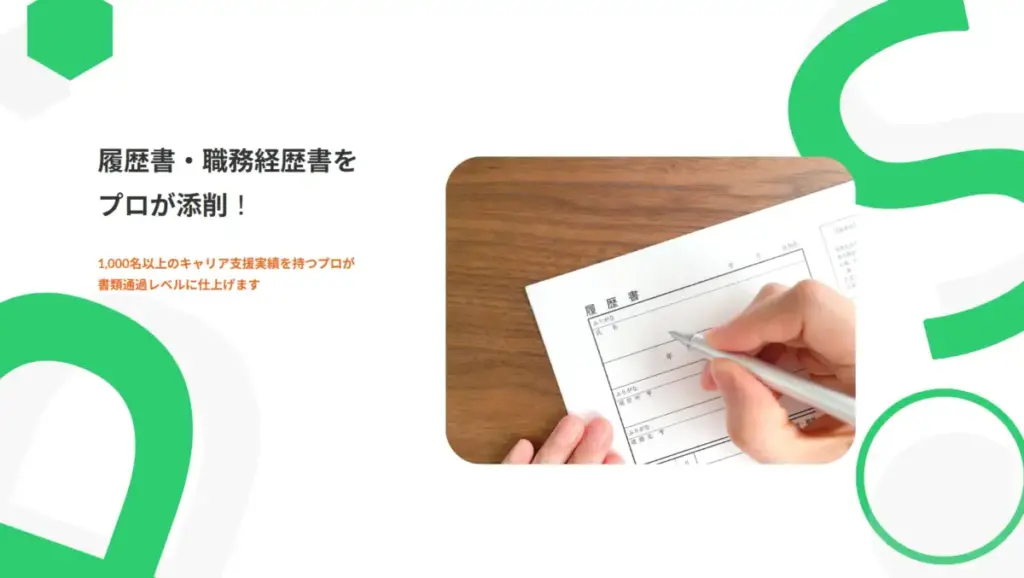
履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。
納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。
書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。
<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」
そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。
会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

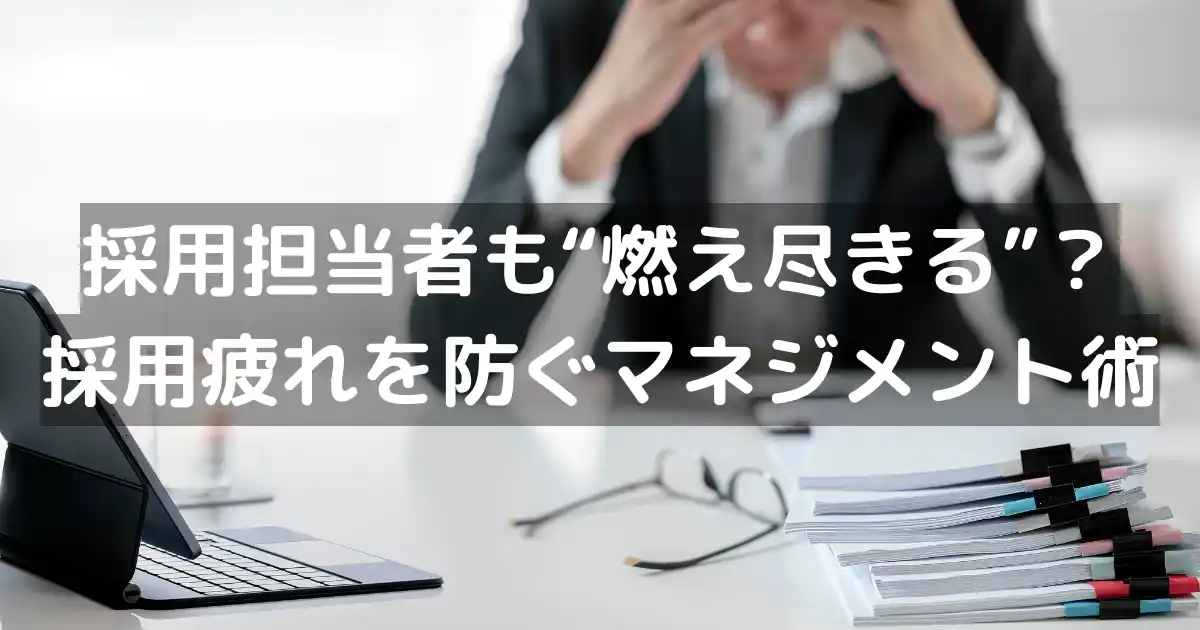
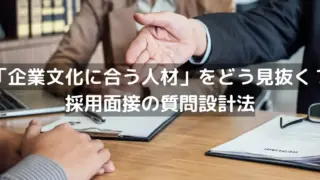
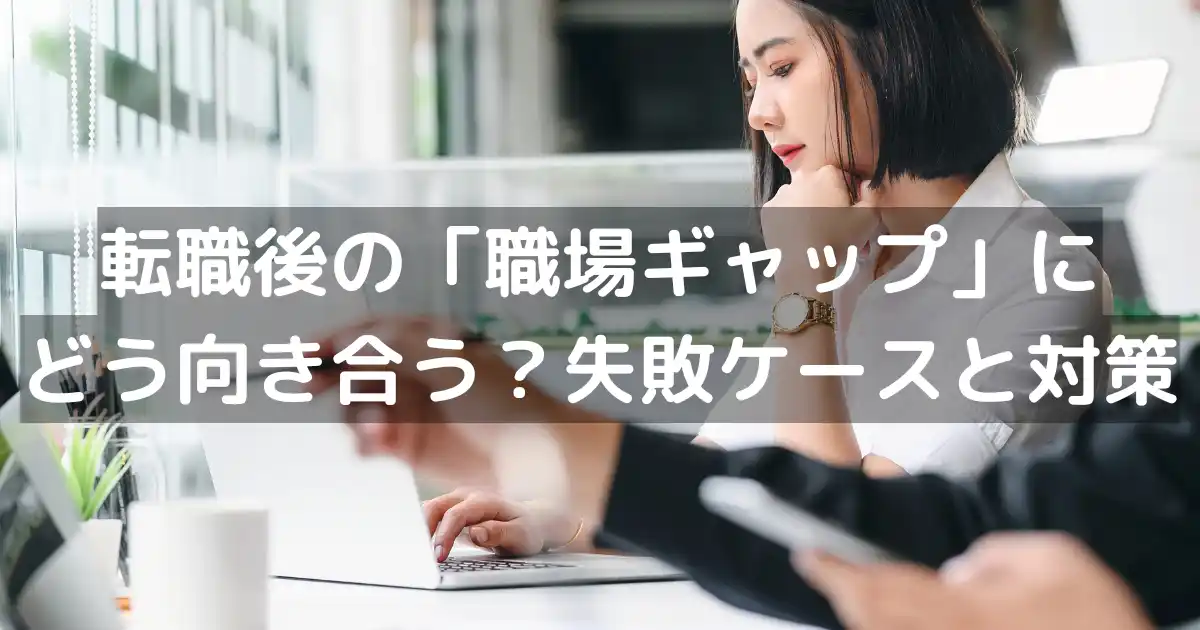
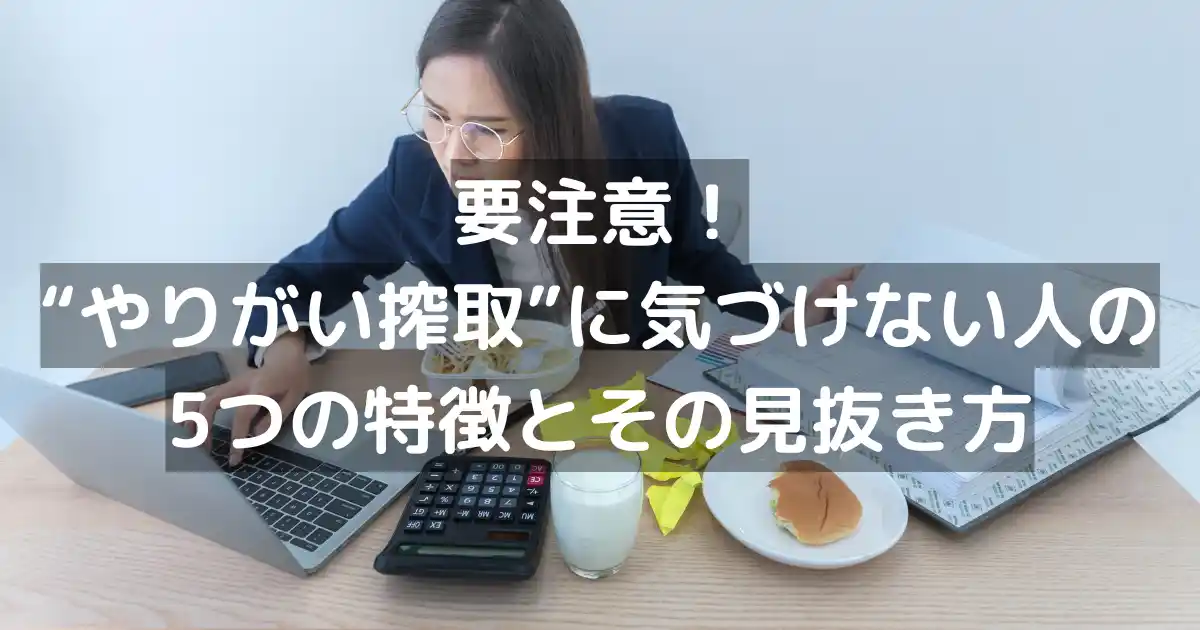
コメント