転職活動を始めたとき、多くの方が最初に悩むのが「職務経歴書を何通も作るべきなのか?」という問題です。
「一度しっかり作れば、それをどこに出してもいいのでは?」と考える人もいれば、「応募先ごとに作り直さないと不利になるのでは」と不安を抱える人もいます。
実は、どちらの考え方も一理あります。
なぜなら、職務経歴書は一度作った基本版が土台になりますが、応募する職種や企業によって“見せ方”を調整した方が、書類選考の通過率が高まるからです。
この記事では、「なぜ職務経歴書を複数用意する必要があるのか」「どんな切り口で作り分けるべきか」を解説し、効率的に対応できる実践ステップをご紹介します。
職務経歴書を複数用意する必要性

では、まずは複数パターンの職務経歴書を用意する意味について考えてみましょう。
企業視点からの理由
採用担当者が知りたいのは「この候補者が、このポジションで成果を出せるかどうか」です。
つまり、同じキャリアでも、応募する職種が変われば評価されるポイントも変わります。
たとえば、営業職を募集している企業なら「売上実績」「新規開拓力」が重視されますが、企画職を募集している企業なら「アイデア創出」「プロジェクト推進力」が評価対象となります。
汎用的な職務経歴書では、採用担当に刺さりにくい可能性があります。
候補者視点からのメリット
一方、候補者自身にとっても複数パターンを作ることは有益です。
経歴の見せ方を変えることで、自分の経験の棚卸しになり、キャリアの幅を再発見できるからです。
たとえば同じ「5年間の営業経験」を振り返っても、「売上の成果」として語れば営業職に強みをアピールでき、「顧客ニーズの分析力」として語れば企画職にも通用します。
また、心理的なメリットも考えられます。
複数パターンを用意し、応募職種に合わせて自分の強みが整理できていると、「このポジションで自分は活躍できる」という思いを強く持てるようになりやすいです。
これは面接での自信にも繋がり、結果として採用担当者への印象も良くなります。
つまり、単なる書類作成作業ではなく、自己理解と面接準備の一環と捉えることができます。
どんな基準で作り分けるのか

では、具体的にどんな基準で分ければよいのでしょうか。
基本は「応募職種ごとに、評価されやすい経験・スキルを強調する」ことです。
職種別の分け方の基本
代表的な以下のような職種だと、たとえばこのようなポイントを強調します。
・営業系
売上実績、達成率、顧客数の拡大など「数字で示せる成果」
・企画系
新規プロジェクトの立ち上げ、課題解決のアイデア、改善施策
・管理系(マネジメント職)
チーム人数、育成実績、組織改善の取り組み
・専門職(IT、士業、デザイナーなど)
技術スキル、資格、実績の具体例
・マーケティング系
Web集客数、CPA/ROAS改善実績、企画から実行までのPDCAサイクル
・事務・アシスタント系
効率化の具体例、チームサポート実績、正確性やスピードに関するエピソード
同じ経験でも見せ方を変える

同じ経験でも強調するポイントで面接官に与える印象を大きく変えることができます。
例えば、営業職として「新商品を担当し、売上を前年比120%に伸ばした」という経験をもっているとします。
営業職向けなら「売上120%達成」「新規顧客開拓50件」と成果を数字で強調すると、営業としての能力をアピールしやすいです。
一方、企画職向けなら「顧客ニーズの調査をもとに新商品の販売戦略を企画し、売上を120%に伸ばした」と企画・分析力にフォーカスすることで、企画職としての力を分かりやすく示すことができます。
つまり、同じ経験でも切り口を変えることで、まったく異なる価値として伝わるのです。
作り直すのではなく“調整”する
「職務経歴書を複数作る」といっても、毎回ゼロから作り直す必要はありません。
基本版を作り、それをベースに応募先の職種や企業に合わせて部分的に修正していけば十分です。
作り分けの実践ステップ

では、実際にどう作り分ければ効率的なのでしょうか。
以下のステップで進めるのがおすすめです。
ステップ1:基本版を作成する
まずは自分のキャリアを網羅的にまとめた“基本職務経歴書”を作ります。
すべての経験・成果を一度整理しておくことで、どの職種にも応用が利きます。
ステップ2:応募先の求人票を分析する
求人票をよく読み、求められるスキルや経験を確認します。
キーワード(例:「営業経験3年以上」「プロジェクト推進力」など)を拾い出すとわかりやすいです。
ステップ3:アピールポイントを取捨選択する
求人で求められている要素に合致する経験を強調し、直接関係ないものは簡潔に記載するか省略します。
ステップ4:表現を調整する
営業向けなら「売上実績」、企画向けなら「工夫や改善」、マネジメントなら「育成人数や組織改善」など、表現の角度を変えます。
実際には「7割は基本版を共通で使い、残り3割を職種別にカスタマイズする」くらいのバランスがおすすめです。
これなら負担も大きくなく、効率よく応募できます。
応用編:企業カルチャー・フェーズへの調整
職種で分けることが基本ですが、さらに応募する企業のカルチャーや成長フェーズに合わせて微調整を加えると、通過率は一層高まります。
・ベンチャー企業・成長フェーズ
「自ら考え行動した経験」「失敗を恐れず挑戦したエピソード」「スピード感」などを強調し、即戦力性と自主性をアピールします。
・大手企業・安定フェーズ
「組織内での調整力」「規定・プロセス遵守の正確性」「大規模プロジェクトでの貢献」などを強調し、チームワークと信頼性をアピールします。
もちろん、必ずしもベンチャーと大手企業という分け方のみで上記アピールポイントが適切とは限らないので、あくまで企業別で判断していくことが重要です。
職種が同じでも、企業が求める人物像は異なります。
求人情報だけでなく、企業サイトのミッションや代表メッセージまで読み込むと、調整すべきポイントが見えてきます。
作り分ける際の注意点

複数パターンを作るときに気をつけたい点もあります。
・嘘や誇張は絶対にNG
強調する部分を変えるのは問題ありませんが、事実をねじ曲げたり誇張するのは避けましょう。
これくらいなら大丈夫と思うかもしれませんが、日々多くの候補者と接する面接官からみると、少し深堀するれば、そういった嘘は驚くほどあっさりバレてしまうものです。
・管理の工夫が必要
複数の職務経歴書を作ると、どれがどの企業向けだったか分からなくなることがあります。
ファイル名に「営業用」「企画用」とつける、応募管理シートで記録するなどの工夫が有効です。
意外と忘れがちなひと手間ですが、こういった工夫がよりスムーズな転職活動の助けとなります。
・更新・修正を忘れない
転職活動中に新しい成果や実績が出ることもあります。
パターンごとに最新版へ更新することを忘れないようにしましょう。
まとめ

職務経歴書は「何通もゼロから作る」必要はありませんが、応募する職種やポジションごとに調整する工夫が欠かせません。
同じ経験でも、営業職向けには「数字」、企画職向けには「アイデア力」、管理職向けには「マネジメント力」と見せ方を変えることで、企業からの評価が大きく変わります。
最初から完璧に作り分ける必要はありません。
まずは基本版を1通完成させ、そこから応募先に合わせて2〜3パターンを作ってみることから始めましょう。
少しの工夫が、書類通過率の向上、ひいてはキャリアの可能性を広げる第一歩となります。
「自分のケースだとどうしたら…」そう感じたら、プロの力を借りてみませんか?
「自分の場合どのようにパターンを分ければいいか不安…」「もっと魅力的にみせたい」という方は、プロの視点での添削がおすすめです。ストローラー株式会社では
▶応募職種別の書類カスタマイズ
▶誤字脱字含む表現のチェック
▶企業ごとに魅力的な履歴書・職務経歴書の作成サポート
など、1,000名以上のキャリア支援を行ってきたプロによる応募書類の添削など、様々なキャリア支援サービスをご提供しています。プロに相談しつつ、次の一歩を踏み出してみたい方は、こちらの詳細ページよりご確認ください。
※初回相談は無料です
<書類通過パス>
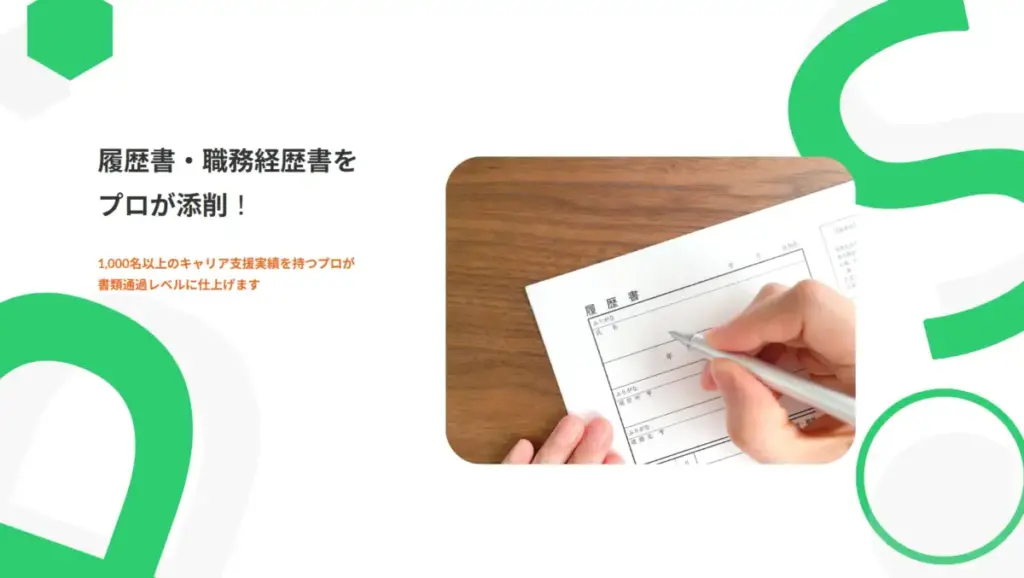
履歴書・職務経歴書のそんなお悩みを、人材のプロが解決します。
納品までの添削は何回でも可能!文字数や職歴数による追加料金も一切発生しません。
書類通過にむけた修正アドバイス付きで、あなたの応募書類のクオリティを向上させます。
<キャリア相談ルートパス>

そんなキャリアの悩みに、1カ月間プロが全力伴走します!
✓ LINEやメールで、1カ月間いつでも何度でも相談OK
✓ Zoom/Meetで1対1の本格キャリア相談(60分)つき
「ちょっと聞いてほしい」から「人生の選択」まで、一緒に考えます。
<自分退職ガイドパス>

「どうやって会社に話せばいい?」「退職前に準備すべきことは?」「法律知識も必要?」
そんな不安、すべてお気軽にご相談ください。
会社への伝え方・書類作成・退職完了まで、丁寧にガイドします。

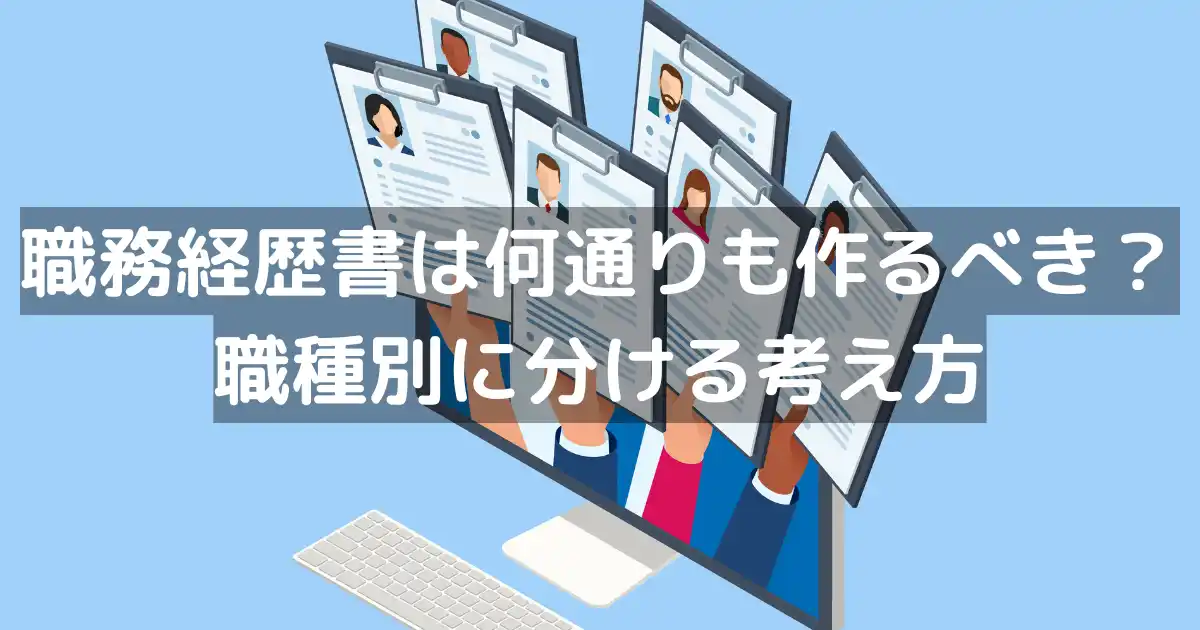
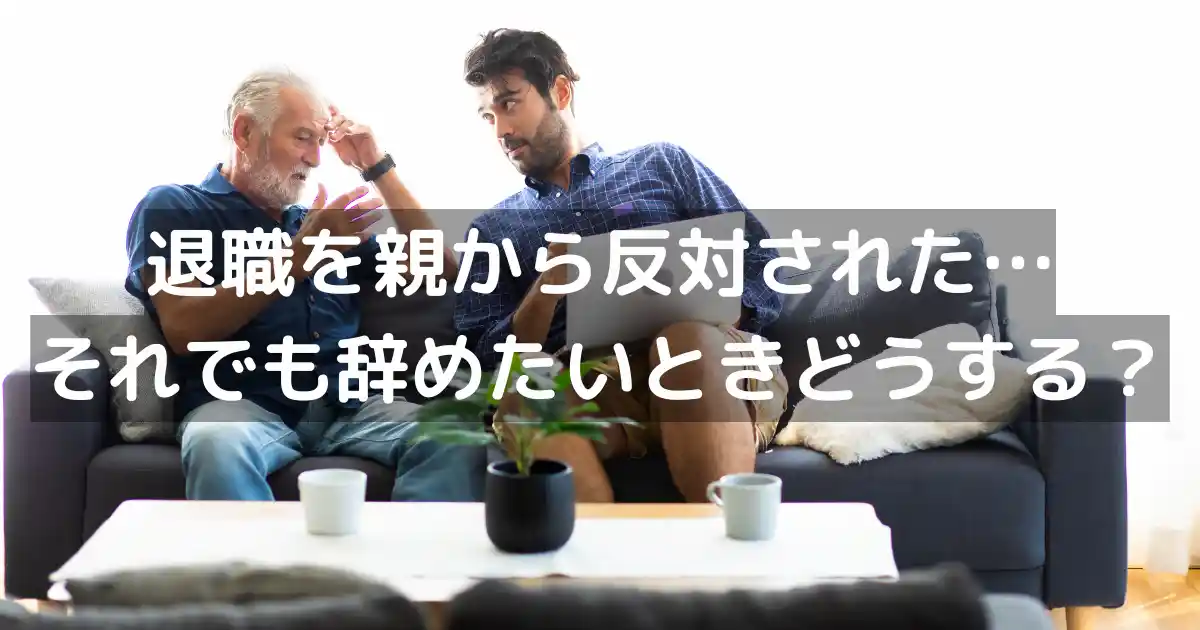
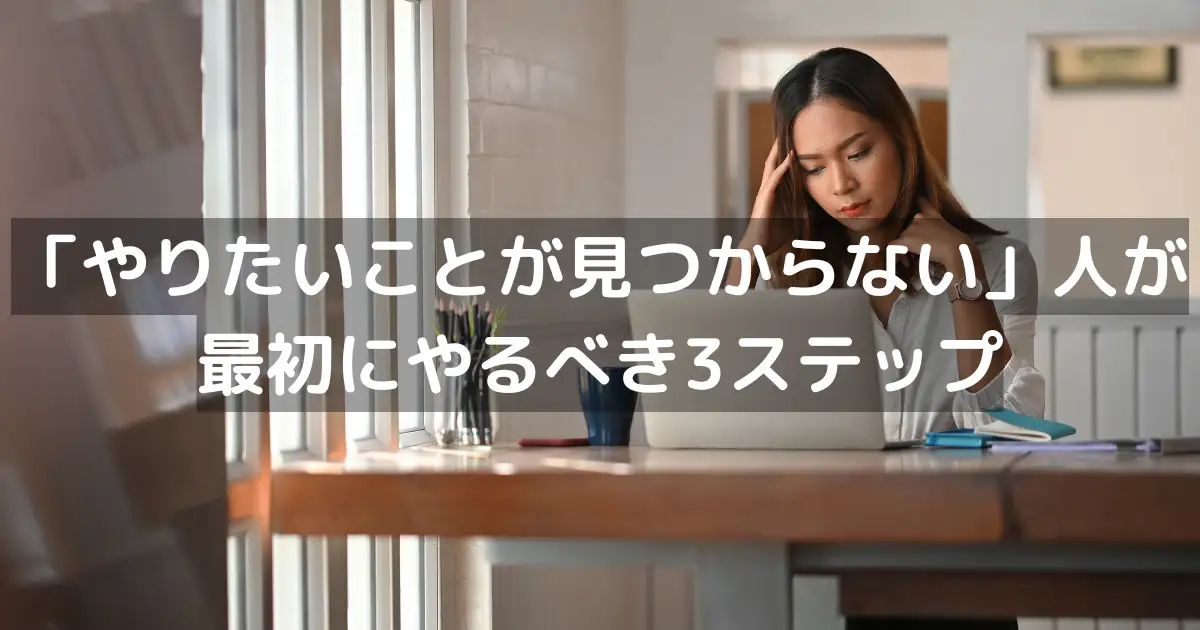
コメント